ソフト食とは?作り方や導入方法を紹介
ソフト食とは、歯や咀嚼に困難を感じる人のための食事形態です。
やわらかく、飲み込みやすい素材を使って調理した料理のことを指します。
高齢者や術後の患者さん、嚥下障害のある方などに適しています。
柔らかな食感で咀嚼が楽で、摂取しやすいのが特徴です。
高齢者の介護で食事は非常に重要です。噛む力や飲み込む力が低下している高齢者の食事の中でも用いられることが多いのが「ソフト食」。ではソフト食とはどのようなものなのでしょうか。今回はソフト食の特徴や作り方についてご紹介します。
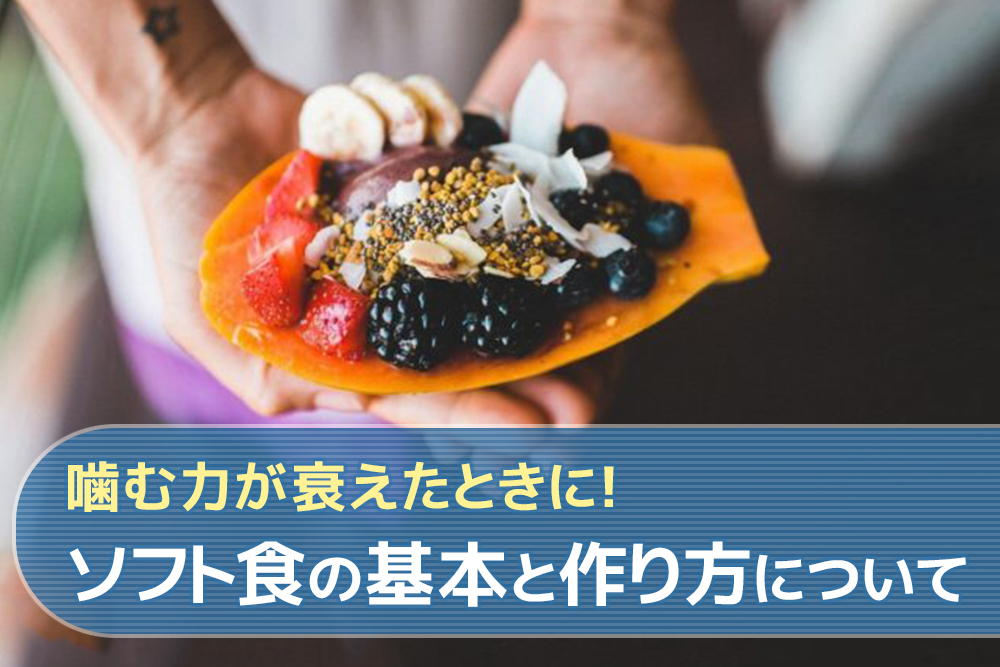
- 目次
- 1. ソフト食とは?
- 2. ソフト食の特徴
- 2-1. 噛む必要が少ない
- 2-2. 飲み込みやすい
- 2-3. 食べやすい形状
- 2-4. 食べ応えがある
- 2-5. 幅広い栄養素を含む
- 3. ソフト食の作り方
- 3-1. 食材の下ごしらえ
- 3-2. 調理方法
- 3-3. 水分量の調整
- 3-4. 彩りや食感への配慮
- 3-5. 嗜好性への配慮
- 4. ソフト食の導入方法は?
- 4-1. アセスメントと計画
- 4-2. 徐々の移行
- 4-3. 食べやすさと栄養のバランス
- 4-4. 段階的な移行
- 4-5. モニタリングと評価
- 5. ソフト食の具体的な献立例
- 5-1. 主菜
- 5-2. 副菜
- 5-3. 主食
- 5-4. デザート
- 6. ソフト食の活用場面と効果
- 6-1. 高齢者の食事
- 6-2. 術後の食事
- 6-3. 障害者の食事
- 6-4. 嚥下訓練の食事
- 7. ソフト食(やわらか食)
- 8. 高齢者ソフト食の特徴
- 9. 高齢者ソフト食の位置づけと導入ステップ
- 10. ソフト食の作り方
- 11. ソフト食の食材ごとの調理ポイント
- 12. まとめ
01ソフト食とは?
01ソフト食の特徴
1-1噛む必要が少ない
ソフト食の最大の特徴は、噛む必要が極めて少ないことです。 歯や咀嚼力が低下した高齢者や術後患者、嚥下障害のある人などにとって、ソフト食は理想的な食事形態となります。 ソフト食は、やわらかく滑らかな食感が特徴です。 ミキサーやフードプロセッサーを使ってペースト状にしたり、煮込みながら柔らかく調理したりと、加工を施すことで噛む必要がほとんどなくなり、ほとんど歯を使わずに飲み込めるため、高齢者の口腔機能の低下を補うことができます。 このように、ソフト食は低咀嚼でも安全に摂取できる食事形態です。 よく噛まなくても飲み込めるため、胃腸への負担も少なく、嚥下機能の低下した人でも誤嚥のリスクが低減されます。
1-1飲み込みやすい
ソフト食の大きな特徴の1つは、飲み込みやすいという点です。 歯や咀嚼力、嚥下機能が低下した高齢者や術後患者、あるいは嚥下障害のある人にとって、ソフト食は理想的な食事形態となります。 ソフト食は、ペースト状やとろみのある滑らかな質感が特徴です。 滑らかな食感のソフト食は、舌で押し流すように飲み込めるため、嚥下に難がある人でも安全に摂取できます。 誤嚥のリスクが低減されるため、肺炎などの合併症を予防する効果も期待できるでしょう。
1-1食べやすい形状
ソフト食の大きな特徴の1つに、食べやすい形状があげられます。 歯や咀嚼力、嚥下機能が低下した高齢者や術後患者などにとって、ソフト食は理想的な食事形態となります。 ソフト食は、ペースト状やとろみのある滑らかな質感が特徴です。 食べ物をほとんど噛まずに飲み込めるため、高齢者の低下した咀嚼機能を補うことができるでしょう。 これらの加工によって、ソフト食は飲み込みやすい滑らかな質感になります。 スプーンですくって口に運べるため、手指の機能が低下した人でも食べやすくなります。 また、薄いとろみをつけることで、食べ物がこぼれにくくなり、食事中の事故リスクも軽減されます。
1-1食べ応えがある
ソフト食の特徴の1つに、食べ応えがあるという点があります。 ソフト食は、歯や咀嚼力、嚥下機能が低下した高齢者や術後患者などにとって理想的な食事形態ですが、単に柔らかいだけではなく、適切な食べ応えも確保されています。 この結果、ペースト状やとろみのある、なめらかな質感が特徴となります。 一方で、適切な食材の選択や調理方法の工夫によって、ソフト食にも食べ応えが与えられているでしょう。 たんぱく質の補給には肉や魚、カロリー補給には芋やパンなどを使うことで、栄養バランスのとれた食事になります。 噛む必要が少なくても満足感を得られるよう、食感にも配慮されているのがソフト食の特徴です。 このように、ソフト食は飲み込みやすさと食べ応えのバランスが取れた、高齢者や術後患者にとって理想的な食事形態といえるでしょう。
1-1幅広い栄養素を含む
ソフト食の大きな特徴の1つに、幅広い栄養素を含んでいることがあげられます。 ソフト食は、歯や咀嚼力、嚥下機能が低下した高齢者や術後患者などの食事サポートに適しており、これらの患者にとって必要な栄養を効果的に摂取できる食事形態となっています。 加工によって、食材本来の栄養素を損なうことなく、高齢者でも簡単に摂取できるのがソフト食の特徴です。 たんぱく質の補給には肉や魚、炭水化物の補給には穀物や芋類、ビタミンやミネラルの補給には野菜や果物といった具合に、様々な食材を使うことで、必要な栄養素をバランス良く摂取できるのがソフト食の大きな利点です。 ソフト食は、噛む必要が少なく、飲み込みやすいため、嚥下機能の低下した高齢者でも安心して食べられます。 同時に、豊富な栄養素を含むことから、患者の健康維持や回復に寄与することができるのです。
01ソフト食の作り方
1-1食材の下ごしらえ
肉類や魚介類は細かく刻むか、ミンチ状にします。野菜は皮をむき、食べやすい大きさに切る必要があります。 また、芋類やパン類なども適切な大きさに切り分けてから、ゆでたり煮たりと柔らかくしていきます。 これらの食材は、ミキサーやフードプロセッサーなどで細かくすり潰したり、圧力鍋を使って長時間煮込んだりと、様々な調理方法を組み合わせて、なめらかなペースト状や滑らかなとろみ状の食感に仕上げていきます。 食材の下ごしらえでは、噛む必要がなく、飲み込みやすい質感を作り出すことが重要。 ただし、単に柔らかくするだけでなく、食材本来の風味や食感も残すよう心がけることも大切です。 こうした細かな下ごしらえを行うことで、ソフト食は高齢者や術後患者でも安全に、そして満足感を持って食べられるようになるのです。
1-1調理方法
肉類や魚、卵などのタンパク質性食材は、煮込みや蒸し焼きなどの湿式調理が適しています。 長時間の加熱によって軟らかく仕上がり、なめらかな食感になります。 また、圧力鍋を使えば、短時間でより柔らかな仕上がりが得られるでしょう。 一方、野菜は蒸すか、長時間煮込むことで細かく崩れやすい食感に仕上がります。 ミキサーやフードプロセッサーを使って、さらに滑らかなペースト状に整えることも可能です。 穀物類やイモ類は、やわらかく煮崩れるまで時間をかけて加熱するのがポイントです。 あらかじめ水分を多めに加えておくと、より滑らかなペースト状に仕上がります。 これらの食材を組み合わせ、さまざまな調理法を駆使して、ペースト状やとろみのあるなめらかな質感のソフト食を作り上げていきます。 こうした細かな工夫を凝らすことで、高齢者や術後患者でも食べやすく、かつ必要な栄養素を逸することなく摂取できるソフト食が完成するのです。
1-1水分量の調整
ペースト状のソフト食を作る場合、食材をミキサーやフードプロセッサーでスムーズに撹拌できるよう、適量の水や汁物を加えることが不可欠です。 ただし、水分が多すぎると、かえって水っぽい食感になってしまうので、食材の性質に応じて加減します。 一方、とろみのあるソフト食の場合は、水分量を控えめにし、トロッとした食感が得られるよう工夫します。 でんぷん質の食材を使ったり、とろみ調整剤を加えたりすることで、適度なとろみを出すことができるでしょう。 また、ソフト食は温かい状態で提供されることが多いため、熱によって水分が蒸発しやすくなります。 温かく保つ工夫と共に、必要に応じて途中で水分を足すなど、適切な水分量を維持するよう気をつける必要があります。 このように、ソフト食の水分量は、食材の種類や調理方法、提供温度などを総合的に勘案しながら、適切に調整していくことが重要なのです。
1-1彩りや食感への配慮
見た目の彩りについては、色合いの異なる食材を組み合わせることで、単調にならないよう工夫します。 例えば、緑色の野菜ペーストに、オレンジ色のにんじんや赤色のトマトペーストを加えるなど、彩りを出すのがポイントです。 食感については、ペースト状のソフト食だけでなく、歯ごたえのある繊維質の食材も取り入れることで、口の中で楽しめる食体験を演出できます。 ささがきのにんじんや刻み海苔、微細なパン粉など、適量を加えると良いでしょう。 さらに、トッピングにも工夫を凝らすと、見た目の華やかさにもつながります。 例えば、ゆで卵の黄身やみじん切りの野菜、ハーブなどを散りばめると、彩りが一層鮮やかになります。 こうした配慮により、ソフト食は見た目にも食べごたえのある、魅力的な仕上がりになるのです。 高齢者や術後患者の食事を彩り豊かで楽しい体験にすることができるでしょう。
1-1嗜好性への配慮
個人の味嗜好に合わせて調味料の量や組み合わせを調整することが肝心です。 塩分控えめでも、しっかりとした味付けを心がけましょう。 醤油やみそ、ドライハーブなどを上手に使うと良いでしょう。 また、ソフト食は彩りや食感の工夫が必要ですが、そこにも嗜好性を反映させます。 例えば、馴染み深い家庭料理の味わいを再現するなど、なじみのある風味を活かすのがポイントです。 さらに、個人の好み別にバリエーションを作ることも重要です。 肉や魚、野菜など、お好みの食材を中心に据えたペーストや、デザート感覚のフルーツペーストなど、様々なメニューを用意すると良いでしょう。 このように、ソフト食作りにおいては、単に食べやすさだけでなく、食べる人の嗜好性にも十分に配慮することが、おいしく食べられる食事につながるのです。
01ソフト食の導入方法は?
1-1アセスメントと計画
ソフト食の導入にあたっては、まずアセスメントを行い、個人の状態に応じた適切な計画を立てることが重要です。 はじめに、患者の口腔機能や嚥下機能、咀嚼能力などを評価します。 専門家による詳細な検査を行い、どの程度の軟らかさや粘性が必要かを確認し、食事時の姿勢や介助の必要性なども把握します。 次に、患者の基礎疾患や経過、栄養状態なども考慮して、ソフト食の具体的な内容を検討し、必要なエネルギー量や栄養素バランスを算出し、適切な食事形態を決定し、彩りや食感にも配慮しつつ、個人の嗜好性にも合わせた献立を立て、ソフト食への移行計画を立てます。 徐々に固形物を減らし、ペースト状のものを増やしていくなど、段階的な移行が望ましいでしょう。 また、食事時の介助方法や、水分補給の必要性についても検討します。 このように、ソフト食の導入には、患者個人の状態を丁寧にアセスメントし、最適な食事内容や提供方法を計画的に立案することが重要です。 専門家チームによる綿密な検討と、患者の状況に合わせた柔軟な対応が求められるでしょう。
1-1徐々の移行
ソフト食への移行は、一気に切り替えるのではなく、徐々に行うことが重要です。 これにより、患者の身体的・精神的な負担を最小限に抑えながら、適切な食事摂取を促すことができます。 まず、現在の食事形態から、少しずつソフト食に近づけていきます。 例えば、常食の一部をミキサー加工したものに置き換えるなど、徐々に固さを弱めていきましょう。 このとき、食材の組み合わせや調理方法を工夫し、見た目や香りにも配慮して、患者の食欲を引き出します。 次に、ソフト食への移行に合わせて、食事時の介助方法も調整します。 介助の度合いや、食事姿勢の工夫など、患者の状態に合わせて最適な方法を検討します。 これにより、スムーズな食事摂取を実現できるでしょう。 さらに、水分補給にも注意を払います。 ソフト食への移行に伴い、水分摂取量が不足しがちになるため、水分量の確認や、ゼリー状の水分補給など、適切な方法を検討します。 このように、ソフト食への移行は段階的に行い、患者の身体的・精神的な負担を最小限に抑えることが重要です。 また、食事形態や介助方法、水分補給の工夫など、患者の状態に合わせた総合的なケアが必要不可欠です。
1-1食べやすさと栄養のバランス
ソフト食を導入する上で、食べやすさと栄養のバランスを両立することが重要です。 患者が安心して楽しく食事を摂取できるよう、適切な食事形態と、必要な栄養素の確保が求められます。 まず、食べやすさの観点から、細かく刻んだり、ミキサーにかけたりと、患者の咀嚼・嚥下能力に合わせてソフト食の形態を調整します。 ペースト状や泥状のものは飲み込みやすく、粘性のコントロールも重要です。 一方で、栄養面では、患者の年齢や病状を考慮し、必要なエネルギーや栄養素を十分に確保します。 たんぱく質や、ビタミン・ミネラルなどを意識的に取り入れるよう、メニューを立案します。 さらに、嗜好性にも留意し、見た目の工夫や、なじみのある味付けを取り入れることで、食事への意欲を引き出します。 個人差も大きいため、患者の嗜好を丁寧に把握し、好みに合わせてメニューを展開することが大切です。 このように、ソフト食の導入においては、食べやすさと栄養のバランスを両立させることが重要です。 患者一人ひとりの状態に合わせた最適な食事形態と、必要な栄養素の確保が、健康的な食事につながるのです。
1-1段階的な移行
ソフト食への段階的な移行は、患者の身体的・精神的な負担を最小限に抑えるために重要です。 一気に大きな変化を強いるのではなく、徐々に食事形態を調整していくことで、患者が安心して食事に取り組めるようサポートすることができるでしょう。 まず、初期段階では、常食の一部をミキサー加工したりきざみ食にするなど、少しずつ食べやすさを高めていきます。 このとき、見た目や香り、味付けにも注意を払い、患者の食欲を損なわないよう工夫します。 次の段階では、ソフト食への移行を本格化させ、徐々に常食をソフト食に置き換えていきます。 この際は、患者の咀嚼・嚥下能力を見極め、適切な固さや粘性のソフト食を提供し、段階的な移行により、患者の体調変化にも柔軟に対応できるでしょう。 さらに、食事介助の方法も合わせて調整し、患者の状態に合わせて、介助の度合いや食事姿勢などを最適化することで、スムーズな食事摂取を実現します。 このように、ソフト食への移行は焦らず段階的に行うことが重要です。 ゆっくりとした変化に寄り添いながら、患者の体調や嗜好に合わせて柔軟に対応することで、安心して食事に取り組めるよう支援できるのです。
1-1モニタリングと評価
ソフト食の導入においては、患者の状態を継続的にモニタリングし、評価を行うことが重要です。 これにより、患者の状態に合わせて柔軟に対応し、効果的なソフト食の提供を実現することができるでしょう。 まず、食事摂取量や体重変化、便の状態など、患者の栄養状態を定期的に確認します。 これにより、ソフト食の栄養価が適切であるかを判断し、必要に応じて調整を行います。 また、患者の咀嚼・嚥下機能についても注意深く観察し、食事介助の方法や食事形態の変更の必要性を検討し、食事時の様子を詳細に記録することで、徐々に改善されているかどうかを把握できるでしょう。 アンケートやインタビューなどを通じて、食事に対する意欲や満足感、生活の質の向上を確認し、患者の主観的な評価を取り入れることで、ニーズに合った食事提供につなげられます。 このように、ソフト食の導入においては、継続的なモニタリングと評価が欠かせません。 患者の状態を丁寧に把握し、随時フィードバックを得ながら、最適な食事形態や介助方法を見出していくことが重要です。
01ソフト食の具体的な献立例
1-1主菜
やわらかく煮込んだ肉料理がおすすめです。 牛肉や豚肉を徹底的に柔らかく煮込むことで、ソフトな食感に仕上がります。 例えば、牛肉のすき煮や豚の角煮など、しっかりとした味付けの煮込み料理が人気です。 魚介類を使ったメニューも人気です。 シンプルに蒸した魚や、ホワイトソースをかけたホキなどが適しています。 骨から外した身を使うことで、歯ぐきでつぶせるようなソフトな質感を実現できます。 卵料理もソフト食に適しています。 ふわふわの卵焼きやオムレツ、スクランブルエッグなどが食べやすいです。 トロトロの質感に仕上げることで、歯ぐきでつぶせる食感を実現できます。 これらの主菜に合わせて、やわらかい根菜類や豆腐など、ソフトな副菜を組み合わせると良いでしょう。 ソース類も、とろみをつけるなどして食べやすさを高めます。 このように、肉、魚介、卵料理といった主菜を、徹底的に柔らかく調理することで、ソフト食におすすめの献立が作れます。
1-1副菜
やわらかく煮込んだ根菜類がおすすめです。 例えば、じっくり煮込んだ里芋やサツマイモ、ゴロゴロとした食感のやわらかいかぼちゃなどが良いでしょう。 水分をたっぷりと含んだ柔らかな質感が特徴です。 豆腐料理もソフト食に適しています。 とろとろの手作りの湯豆腐や、ミキサーにかけてなめらかな舌ざわりに仕上げた豆腐のムース風など、上品な口当たりが特徴です。 また、やわらかく調理した野菜のピューレ状の料理もおすすめです。 ほうれん草やかぶ、トマトなどを煮込んでミキサーにかけ、とろみをつけて仕上げ、繊維感がなくなり、なめらかな食感に仕上がります。 さらに、ゆでた野菜を細かくきざんで、やわらかくしたものもよいでしょう。 例えば、やわらかくゆでた小松菜やにんじん、ズッキーニなどをきざんで、和え物やサラダ風に仕立てます。 これらの副菜に合わせて、ソフトな質感の和え物やスープ、デザートなども組み合わせると良いでしょう。
1-1主食
やわらかく煮込んだご飯がおすすめです。 通常の白米を長時間かけてやわらかく煮込むことで、ひと口でつぶせるほど柔らかな食感に仕上がり、具だくさんの雑炊や、オートミールのようなとろみのあるご飯も適しています。 パンも柔らかいものを選ぶと良いでしょう。 食パンは耳を取り除いたり、食べやすい大きさに切ったものがおすすめです。 また、蒸しパンや焼きおにぎりなど、やわらかい質感のパン類も向いています。 さらに、うどんやそばなどの麺類も適しています。 よく煮込んで柔らかく仕上げたうどんや、やわらかい食感のそば湯葉など、歯ぐきでつぶせるような柔らかさが特徴です。 また、粥や雑炊、スープなども主食として活用できるでしょう。 とろみを付けて滑らかな口当たりに仕上げることで、飲み込みやすい質感になります。 これらの主食に合わせて、やわらかい副菜や、とろみのあるソースなども組み合わせることで、さらに食べやすい献立になります。
1-1デザート
なめらかなプリンやゼリーがおすすめです。 卵やミルクを使ったクリーミーなプリンは、滑らかな口当たりが特徴です。 また、フルーツの果汁を使ったフルーツゼリーは、さっぱりとした食感で消化もよいでしょう。 パウンドケーキやスポンジケーキなども適しています。 水分を多く含み、ふわふわとした柔らかい質感のものが良いでしょう。 アイスクリームやアイスミルクなど、溶けやすい冷たいデザートもおすすめです。 さらに、とろとろのプディングやムースも向いています。 ミキサーにかけてなめらかにしたり、卵や乳製品を使ってとろみを出すことで、なめらかな口あたりに仕上がります。 チョコレートやフルーツなどを混ぜると、味わいも豊かになります。 ゼリー菓子やゼリー寄せも選択肢の一つです。フルーツの果肉がゼリーに包まれた、とろけるような食感が特徴的です。 グラノーラやビスケットをトッピングすると食べ応えも出ます。 さらに、やわらかい食感のプリンやムースを冷やしたカスタードクリームなども、デザートとして活用できるでしょう。 これらのデザートは、患者さんの好みや嗜好に合わせて、味付けや素材を調整することが大切です。
01ソフト食の活用場面と効果
1-1高齢者の食事
高齢者は加齢に伴い、咀嚼力や嚥下機能の低下が見られることが多くなります。 固い食べ物を食べるのが困難になったり、飲み込みにくくなったりするのです。 このような状況では、ソフト食の活用が大きな効果を発揮します。 ソフト食は、やわらかい食感で飲み込みやすい特徴があり、歯ぐきでつぶせるような柔らかさや、とろみのある質感が特徴です。 そのため、高齢者でも問題なく摂取できるのが大きなメリットです。 また、ソフト食は消化吸収も良好です。胃腸への負担が少ないため、低栄養が懸念される高齢者にも適しています。 適切な栄養バランスを確保しながら、安全に食事をとることができるのです。 さらに、ソフト食は食べやすさが高いため、食欲増進にも効果的です。 柔らかく滑らかな質感が、高齢者の食べ応えを高めます。 食べ残しが少なく、必要な栄養を確実に摂取できるというメリットも大きいでしょう。 このように、高齢者の食事におけるソフト食の活用は非常に重要です。 咀嚼力や嚥下機能の低下した高齢者に適した食事形態として、健康的な食生活を支えるツールとなるのです。
1-1術後の食事
手術後は、胃腸の機能が一時的に低下する場合があります。 固い食べ物を摂取すると、胃腸への負担が大きくなり、消化吸収が悪化する可能性があります。 そのため、ソフト食の提供が不可欠となります。 ソフト食は、やわらかく滑らかな質感が特徴です。 歯ぐきでつぶせるような食感のため、術後の患者さんでも問題なく摂取できます。 また、胃腸への負担が少ないため、消化吸収も良好です。 さらに、ソフト食は食べやすさが高いという利点があります。 手術直後は、食欲の低下や嚥下機能の低下が見られることが多いですが、ソフト食なら摂取しやすくなります。十分な栄養を確実に摂取できるのです。 ソフト食は、術後の回復過程において非常に重要な役割を果たします。 手術後の胃腸機能の回復を促し、必要な栄養素を確実に摂取できるようサポートします。 また、ソフト食は排出物の性状にも良い影響を与えます。 便秘や下痢の予防に効果的で、術後の健康的な排便パターンの確立にも寄与します。 このように、術後の食事におけるソフト食の活用は、患者の早期回復に大きな役割を果たすのです。
1-1障害者の食事
障害によっては、咀嚼や嚥下の機能が低下することがあります。 固い食べ物を食べるのが困難になったり、飲み込みにくくなったりするのです。 このような状況では、ソフト食が大きな効果を発揮します。 ソフト食は、やわらかく滑らかな質感が特徴です。 歯ぐきでつぶせるような食感のため、障害者でも問題なく摂取できます。 また、胃腸への負担が少ないため、消化吸収も良好です。 さらに、ソフト食は食べやすさが高いというメリットがあり、障害によっては、食事動作が不得意になることがありますが、ソフト食なら摂取しやすくなり、必要な栄養を確実に摂取できるのです。 ソフト食は、障害者の食事の質を高めるうえで重要な役割を果たします。 咀嚼や嚥下の問題を抱える障害者にとって、ソフト食は安全・安心して食事ができる選択肢となります。 また、ソフト食は、障害者の自立的な食事動作の獲得にも寄与します。 固い食べ物を避けることで、食事に伴う負担が軽減され、徐々に食事動作の改善が期待できるのです。 このように、障害者の食事におけるソフト食の活用は、健康的な食生活を支えるうえで欠かせない要素といえるでしょう。
1-1嚥下訓練の食事
嚥下訓練とは、嚥下反射の改善や筋力強化を目的とした取り組みです。 訓練に際しては、適切な食形態を選択することが不可欠となります。 その際、ソフト食が最適な選択肢といえるでしょう。 ソフト食は、やわらかく滑らかな質感が特徴です。 これにより、嚥下動作の練習が容易になります。固い食べ物に比べて、咀嚼や嚥下の負担が小さくなるため、徐々に筋力強化を図ることができるのです。 また、ソフト食は安全性が高いという利点もあり、嚥下機能が低下している場合、固い食べ物の摂取は誤嚥のリスクが高まります。 一方、ソフト食なら誤嚥のリスクが小さく、安心して訓練に取り組めます。 さらに、ソフト食は食べやすさも高いという特徴があります。 嚥下訓練では、継続的な摂取が求められますが、ソフト食なら訓練の負担も軽減され、必要な栄養を十分に摂取できるのです。 このように、嚥下訓練における食事にソフト食を活用することは、機能回復を効果的に促進する上で非常に重要な要素といえるでしょう。 咀嚼や嚥下の筋力強化を図りつつ、安全性と食べやすさを両立できるのがソフト食の大きな特徴なのです。
01ソフト食(やわらか食)
「やわらか食」と呼ばれることも多いソフト食。そもそもソフト食とはどのようなものを指すのでしょうか。
1-1食材を一つずつ個別にミキサーにかけて固め直したもの
ソフト食とは、簡単に言えば食材を一つずつミキサーに掛け、それを再度固め直した食事のこと。一度ミキサーにかけることで、あごの筋力が低下して噛む力が弱くなった高齢者でも噛みやすいのが特徴です。さらに、再び固め直しているため、噛んだあとも口の中に残りにくく、まとまりやすいという利点もあります。
また、高齢者の場合には胃腸の働きも衰えているため、消化不良を起こしたり、そもそも食欲を感じないということも珍しくありませんが、もしきちんと食事ができないと、健康状態が低下、生きる意欲を失ってしまうこともあります。
単に食材を柔らかく煮たり蒸したりする食事では消化が難しいこともありますが、ソフト食はミキサーにかけているため消化と吸収が簡単。盛り付けなども普通の食事に近いことから、美味しそうな見た目と香りで食欲をアップさせる効果もあります。
1-2きざみ食やミキサー食のデメリットがカバーされている
ソフト食の特徴は、食材を細かく刻んだ「きざみ食」や、ミキサーにかけた「ミキサー食」のデメリットがカバーされている点にもあります。
そもそも、これらの食事は見た目が悪く、食欲を感じないこともありますが、ソフト食は見た目は普通の食事と変わらないため、食欲不振に陥る心配がありません。
特にミキサー食の場合、食材はすべてペースト状になっているため、何を食べているのか分からないということになってしまうもの。高齢者は身体の状態だけでなく、味を感じる味覚や香りを感じる味覚の働きも衰えているため、さらにどんなものを食べているのか分からなくなり、食事がつまらないものになりがちです。
しかし、ソフト食はミキサーにかけた食材を再び成型しているため見た目が普通食に近く、自分がどのようなものを食べているのかをはっきり認識することができます。
また、高齢者の食事で心配なのが誤嚥。誤嚥は食べ物を飲み込む力や、口の中で咀嚼した食べ物をまとめるの低下によって起こるもので、食物のかけらや水分が気管に入ってしまうことで誤嚥性肺炎につながることもあります。
しかしソフト食の場合にはきざみ食のように口の中でばらばらになってしまうことも少なく、誤嚥を起こしにくいというメリットもあります。
02高齢者ソフト食の特徴
高齢者の心身にとって様々なメリットがあるソフト食。
ソフト食の特徴は食事の見た目と香りを楽しめるという点。この点は食事によって生きる意欲を高めるためには非常に重要です。
食事は誰にとっても楽しみですが、高齢者になると食事を楽しめなくなってしまいがち。しかし、ソフト食を用いることで、いつまでも次の食事を楽しみにするという心の動きが生まれます。
また、歯がない人でも歯茎や舌を使って押しつぶせることや、すでに固まりになっていること、滑りがよいことで喉を通りやすいといった点も重要です。
高齢者は様々な点に身体の衰えが現れますが、その衰える部分は人によって様々。さらに将来の衰えを予想して、早めにミキサー食などを導入した場合、まだまだ元気な部分も弱りがちになってしまいます。
その点でも、つなぎなどを使わず口の中でまとまりやすいソフト食を用いることは、高齢者の健康維持に非常に役立つということができるでしょう。
03高齢者ソフト食の位置づけと導入ステップ
高齢者の介護食には様々な種類があるもの。また、それらの介護食を導入するためには、適切なステップが重要です。
3-1きざみ食:咀嚼機能の低い人
高齢者の介護食の中でももっとも最初に使われるのが「きざみ食」です。きざみ食は、普通食の食材を細かく刻んだ食事のことで、口がなかなか開きにくい人や、固いものを噛む力が弱くなっている人など、咀嚼機能が低下している場合に用いられます。
きざみ食は内容的には普通食とほぼ変わらないことや、何を食べているのかがはっきり分かることなどのメリットもありますが、口の中でばらばらになりやすく誤嚥を起こしやすいというメリットがあります。
最近、食べ物を食べると疲れてしまうという場合や、入れ歯に問題があるという場合に用いるのがよいでしょう。
3-2ミキサー食:嚥下機能の低い人
「ミキサー食」は、食材をミキサーにかけたもので、食べ物の形が残らないことが特徴です。
高齢者の場合、食べ物を噛む力だけでなく飲み込む力も衰えますが、ミキサー食は噛む力と飲み込む力が衰えた人向けの食事。単に食材をミキサーにかけるだけでなく、ゼラチンゼリーなどを使用することでより滑らかに喉を通る状態に仕上げられています。
ミキサー食は、咀嚼と嚥下の機能が低下している場合だけでなく、胃腸が衰えている場合でも消化と吸収が容易に行われるため、高齢者に向いた食事です。
また、ミキサー食で重要なのが水分。ミキサーを回すためにはある程度の水分が必要になるため、ミキサー食は通常よりも多くの水分を補給することができます。
しかし、多くの水分を使うとどうしても味が薄くなり、分量が増加。結果として、食事を残しがちになり、必要な栄養が補給できないということになってしまいます。
さらに、すべてをミキサーにかけてしまうことから、何を食べているのか分からないということになりがちです。
3-3ソフト食:咀嚼から嚥下までしやすい
ソフト食は一度食材をミキサーにかけているため、非常に柔らかい状態。そのため、咀嚼に問題がある人でもスムーズに食事を楽しむことができます。また、ミキサーにかけた食材を再び固めていることから、嚥下も簡単に行うことができます。
また、きざみ食のように誤嚥が起きる可能性も少なくなり、ミキサー食のように食欲が減退してしまうこともありません。
そのため、咀嚼と嚥下の双方または片方だけに問題がある場合にも用いることができます。
3-4導入ステップ
ソフト食は、身体の機能の衰えとともに導入するのが一般的。
ただし、いきなりすべての食事をソフト食にしてしまうよりも、普通食が難しくなったら、まずは食材の煮込み時間を長くしたり、圧力鍋を使用したりする軟菜食を用いましょう。
軟菜食は普通の食事と見た目は変わらないため、食事の楽しみが失われることもありません。また、あごやのどの筋肉を使うことから、衰えの速度を抑える効果も期待できます。
それでも軟菜食が難しい、食が進まないということになった場合、まずおかずのどれかをソフト食に置き換えて少しずつ慣れていくという方法がよいでしょう。
04ソフト食の作り方
高齢者にとってメリットの多いソフト食。では家庭でソフト食を作るときにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
4-1食材選び
ソフト食を作るときには、まず繊維の少ない食材を選ぶことが必要です。繊維質が多いものの場合、ミキサーにかけても繊維が残ってしまうことがあります。
もし肉や魚を使うときには、赤身の部分は避けて脂肪が多く含まれている部位などを選ぶとよいでしょう。
4-2調理の方法
調理を行うときには、片栗粉やゼラチンでとろみをつけることが必要です。もし汁物などがサラサラしていると誤嚥の危険性が高くなります。
また、飲み込みやすくするためにはオリーブオイル、ごま油やバターなどの脂質を使うという方法も。油の香りは食欲を刺激するので、食欲が減退しがちだという場合にも役立ちます。
4-3つなぎを使用
口の中に入れた食材がばらばらになってしまうと、飲み込みにくくなり誤嚥の可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐためには、つぶした食材同士をつなげるための卵や片栗粉、油などを活用します。
また、つなぎを使うと柔らかさを調整できるというメリットも。
歯の状態などにもよりますが、舌でつぶせる程度のほどよい硬さにするとよいでしょう。
05ソフト食の食材ごとの調理ポイント
ソフト食を作るためには、食材によって気を付けたい調理のポイントも異なります。
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
患者さんの状態に合わせてソフト食を作るには、まず嚥下機能の状態を確認することが重要です。
嚥下能力が低下していれば、極めてなめらかなペースト状の食事が適しています。
一方、咀嚼力がある程度残っている場合は、やわらかい食感の料理を提供するのがよいでしょう。
食材の選び方や調理方法を工夫することで、患者さんに合ったソフト食を提供できます。
食事形態は段階的に移行させ、患者の嚥下状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
ソフト食を通じて、患者さんの 生活の質の向上に寄与できるでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
Copyright © 2021 RYO SEKKEI ARCHITECT LEARNING SCHOOL All rights reserved.
1-1食材を一つずつ個別にミキサーにかけて固め直したもの
ソフト食とは、簡単に言えば食材を一つずつミキサーに掛け、それを再度固め直した食事のこと。一度ミキサーにかけることで、あごの筋力が低下して噛む力が弱くなった高齢者でも噛みやすいのが特徴です。さらに、再び固め直しているため、噛んだあとも口の中に残りにくく、まとまりやすいという利点もあります。
また、高齢者の場合には胃腸の働きも衰えているため、消化不良を起こしたり、そもそも食欲を感じないということも珍しくありませんが、もしきちんと食事ができないと、健康状態が低下、生きる意欲を失ってしまうこともあります。
単に食材を柔らかく煮たり蒸したりする食事では消化が難しいこともありますが、ソフト食はミキサーにかけているため消化と吸収が簡単。盛り付けなども普通の食事に近いことから、美味しそうな見た目と香りで食欲をアップさせる効果もあります。
1-2きざみ食やミキサー食のデメリットがカバーされている
ソフト食の特徴は、食材を細かく刻んだ「きざみ食」や、ミキサーにかけた「ミキサー食」のデメリットがカバーされている点にもあります。
そもそも、これらの食事は見た目が悪く、食欲を感じないこともありますが、ソフト食は見た目は普通の食事と変わらないため、食欲不振に陥る心配がありません。
特にミキサー食の場合、食材はすべてペースト状になっているため、何を食べているのか分からないということになってしまうもの。高齢者は身体の状態だけでなく、味を感じる味覚や香りを感じる味覚の働きも衰えているため、さらにどんなものを食べているのか分からなくなり、食事がつまらないものになりがちです。
しかし、ソフト食はミキサーにかけた食材を再び成型しているため見た目が普通食に近く、自分がどのようなものを食べているのかをはっきり認識することができます。
また、高齢者の食事で心配なのが誤嚥。誤嚥は食べ物を飲み込む力や、口の中で咀嚼した食べ物をまとめるの低下によって起こるもので、食物のかけらや水分が気管に入ってしまうことで誤嚥性肺炎につながることもあります。
しかしソフト食の場合にはきざみ食のように口の中でばらばらになってしまうことも少なく、誤嚥を起こしにくいというメリットもあります。
02高齢者ソフト食の特徴
高齢者の心身にとって様々なメリットがあるソフト食。
ソフト食の特徴は食事の見た目と香りを楽しめるという点。この点は食事によって生きる意欲を高めるためには非常に重要です。
食事は誰にとっても楽しみですが、高齢者になると食事を楽しめなくなってしまいがち。しかし、ソフト食を用いることで、いつまでも次の食事を楽しみにするという心の動きが生まれます。
また、歯がない人でも歯茎や舌を使って押しつぶせることや、すでに固まりになっていること、滑りがよいことで喉を通りやすいといった点も重要です。
高齢者は様々な点に身体の衰えが現れますが、その衰える部分は人によって様々。さらに将来の衰えを予想して、早めにミキサー食などを導入した場合、まだまだ元気な部分も弱りがちになってしまいます。
その点でも、つなぎなどを使わず口の中でまとまりやすいソフト食を用いることは、高齢者の健康維持に非常に役立つということができるでしょう。
03高齢者ソフト食の位置づけと導入ステップ
高齢者の介護食には様々な種類があるもの。また、それらの介護食を導入するためには、適切なステップが重要です。
3-1きざみ食:咀嚼機能の低い人
高齢者の介護食の中でももっとも最初に使われるのが「きざみ食」です。きざみ食は、普通食の食材を細かく刻んだ食事のことで、口がなかなか開きにくい人や、固いものを噛む力が弱くなっている人など、咀嚼機能が低下している場合に用いられます。
きざみ食は内容的には普通食とほぼ変わらないことや、何を食べているのかがはっきり分かることなどのメリットもありますが、口の中でばらばらになりやすく誤嚥を起こしやすいというメリットがあります。
最近、食べ物を食べると疲れてしまうという場合や、入れ歯に問題があるという場合に用いるのがよいでしょう。
3-2ミキサー食:嚥下機能の低い人
「ミキサー食」は、食材をミキサーにかけたもので、食べ物の形が残らないことが特徴です。
高齢者の場合、食べ物を噛む力だけでなく飲み込む力も衰えますが、ミキサー食は噛む力と飲み込む力が衰えた人向けの食事。単に食材をミキサーにかけるだけでなく、ゼラチンゼリーなどを使用することでより滑らかに喉を通る状態に仕上げられています。
ミキサー食は、咀嚼と嚥下の機能が低下している場合だけでなく、胃腸が衰えている場合でも消化と吸収が容易に行われるため、高齢者に向いた食事です。
また、ミキサー食で重要なのが水分。ミキサーを回すためにはある程度の水分が必要になるため、ミキサー食は通常よりも多くの水分を補給することができます。
しかし、多くの水分を使うとどうしても味が薄くなり、分量が増加。結果として、食事を残しがちになり、必要な栄養が補給できないということになってしまいます。
さらに、すべてをミキサーにかけてしまうことから、何を食べているのか分からないということになりがちです。
3-3ソフト食:咀嚼から嚥下までしやすい
ソフト食は一度食材をミキサーにかけているため、非常に柔らかい状態。そのため、咀嚼に問題がある人でもスムーズに食事を楽しむことができます。また、ミキサーにかけた食材を再び固めていることから、嚥下も簡単に行うことができます。
また、きざみ食のように誤嚥が起きる可能性も少なくなり、ミキサー食のように食欲が減退してしまうこともありません。
そのため、咀嚼と嚥下の双方または片方だけに問題がある場合にも用いることができます。
3-4導入ステップ
ソフト食は、身体の機能の衰えとともに導入するのが一般的。
ただし、いきなりすべての食事をソフト食にしてしまうよりも、普通食が難しくなったら、まずは食材の煮込み時間を長くしたり、圧力鍋を使用したりする軟菜食を用いましょう。
軟菜食は普通の食事と見た目は変わらないため、食事の楽しみが失われることもありません。また、あごやのどの筋肉を使うことから、衰えの速度を抑える効果も期待できます。
それでも軟菜食が難しい、食が進まないということになった場合、まずおかずのどれかをソフト食に置き換えて少しずつ慣れていくという方法がよいでしょう。
04ソフト食の作り方
高齢者にとってメリットの多いソフト食。では家庭でソフト食を作るときにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
4-1食材選び
ソフト食を作るときには、まず繊維の少ない食材を選ぶことが必要です。繊維質が多いものの場合、ミキサーにかけても繊維が残ってしまうことがあります。
もし肉や魚を使うときには、赤身の部分は避けて脂肪が多く含まれている部位などを選ぶとよいでしょう。
4-2調理の方法
調理を行うときには、片栗粉やゼラチンでとろみをつけることが必要です。もし汁物などがサラサラしていると誤嚥の危険性が高くなります。
また、飲み込みやすくするためにはオリーブオイル、ごま油やバターなどの脂質を使うという方法も。油の香りは食欲を刺激するので、食欲が減退しがちだという場合にも役立ちます。
4-3つなぎを使用
口の中に入れた食材がばらばらになってしまうと、飲み込みにくくなり誤嚥の可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐためには、つぶした食材同士をつなげるための卵や片栗粉、油などを活用します。
また、つなぎを使うと柔らかさを調整できるというメリットも。
歯の状態などにもよりますが、舌でつぶせる程度のほどよい硬さにするとよいでしょう。
05ソフト食の食材ごとの調理ポイント
ソフト食を作るためには、食材によって気を付けたい調理のポイントも異なります。
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
患者さんの状態に合わせてソフト食を作るには、まず嚥下機能の状態を確認することが重要です。
嚥下能力が低下していれば、極めてなめらかなペースト状の食事が適しています。
一方、咀嚼力がある程度残っている場合は、やわらかい食感の料理を提供するのがよいでしょう。
食材の選び方や調理方法を工夫することで、患者さんに合ったソフト食を提供できます。
食事形態は段階的に移行させ、患者の嚥下状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
ソフト食を通じて、患者さんの 生活の質の向上に寄与できるでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
Copyright © 2021 RYO SEKKEI ARCHITECT LEARNING SCHOOL All rights reserved.
ソフト食の特徴は食事の見た目と香りを楽しめるという点。この点は食事によって生きる意欲を高めるためには非常に重要です。
食事は誰にとっても楽しみですが、高齢者になると食事を楽しめなくなってしまいがち。しかし、ソフト食を用いることで、いつまでも次の食事を楽しみにするという心の動きが生まれます。
また、歯がない人でも歯茎や舌を使って押しつぶせることや、すでに固まりになっていること、滑りがよいことで喉を通りやすいといった点も重要です。
高齢者は様々な点に身体の衰えが現れますが、その衰える部分は人によって様々。さらに将来の衰えを予想して、早めにミキサー食などを導入した場合、まだまだ元気な部分も弱りがちになってしまいます。
その点でも、つなぎなどを使わず口の中でまとまりやすいソフト食を用いることは、高齢者の健康維持に非常に役立つということができるでしょう。
03高齢者ソフト食の位置づけと導入ステップ
高齢者の介護食には様々な種類があるもの。また、それらの介護食を導入するためには、適切なステップが重要です。
3-1きざみ食:咀嚼機能の低い人
高齢者の介護食の中でももっとも最初に使われるのが「きざみ食」です。きざみ食は、普通食の食材を細かく刻んだ食事のことで、口がなかなか開きにくい人や、固いものを噛む力が弱くなっている人など、咀嚼機能が低下している場合に用いられます。
きざみ食は内容的には普通食とほぼ変わらないことや、何を食べているのかがはっきり分かることなどのメリットもありますが、口の中でばらばらになりやすく誤嚥を起こしやすいというメリットがあります。
最近、食べ物を食べると疲れてしまうという場合や、入れ歯に問題があるという場合に用いるのがよいでしょう。
3-2ミキサー食:嚥下機能の低い人
「ミキサー食」は、食材をミキサーにかけたもので、食べ物の形が残らないことが特徴です。
高齢者の場合、食べ物を噛む力だけでなく飲み込む力も衰えますが、ミキサー食は噛む力と飲み込む力が衰えた人向けの食事。単に食材をミキサーにかけるだけでなく、ゼラチンゼリーなどを使用することでより滑らかに喉を通る状態に仕上げられています。
ミキサー食は、咀嚼と嚥下の機能が低下している場合だけでなく、胃腸が衰えている場合でも消化と吸収が容易に行われるため、高齢者に向いた食事です。
また、ミキサー食で重要なのが水分。ミキサーを回すためにはある程度の水分が必要になるため、ミキサー食は通常よりも多くの水分を補給することができます。
しかし、多くの水分を使うとどうしても味が薄くなり、分量が増加。結果として、食事を残しがちになり、必要な栄養が補給できないということになってしまいます。
さらに、すべてをミキサーにかけてしまうことから、何を食べているのか分からないということになりがちです。
3-3ソフト食:咀嚼から嚥下までしやすい
ソフト食は一度食材をミキサーにかけているため、非常に柔らかい状態。そのため、咀嚼に問題がある人でもスムーズに食事を楽しむことができます。また、ミキサーにかけた食材を再び固めていることから、嚥下も簡単に行うことができます。
また、きざみ食のように誤嚥が起きる可能性も少なくなり、ミキサー食のように食欲が減退してしまうこともありません。
そのため、咀嚼と嚥下の双方または片方だけに問題がある場合にも用いることができます。
3-4導入ステップ
ソフト食は、身体の機能の衰えとともに導入するのが一般的。
ただし、いきなりすべての食事をソフト食にしてしまうよりも、普通食が難しくなったら、まずは食材の煮込み時間を長くしたり、圧力鍋を使用したりする軟菜食を用いましょう。
軟菜食は普通の食事と見た目は変わらないため、食事の楽しみが失われることもありません。また、あごやのどの筋肉を使うことから、衰えの速度を抑える効果も期待できます。
それでも軟菜食が難しい、食が進まないということになった場合、まずおかずのどれかをソフト食に置き換えて少しずつ慣れていくという方法がよいでしょう。
04ソフト食の作り方
高齢者にとってメリットの多いソフト食。では家庭でソフト食を作るときにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
4-1食材選び
ソフト食を作るときには、まず繊維の少ない食材を選ぶことが必要です。繊維質が多いものの場合、ミキサーにかけても繊維が残ってしまうことがあります。
もし肉や魚を使うときには、赤身の部分は避けて脂肪が多く含まれている部位などを選ぶとよいでしょう。
4-2調理の方法
調理を行うときには、片栗粉やゼラチンでとろみをつけることが必要です。もし汁物などがサラサラしていると誤嚥の危険性が高くなります。
また、飲み込みやすくするためにはオリーブオイル、ごま油やバターなどの脂質を使うという方法も。油の香りは食欲を刺激するので、食欲が減退しがちだという場合にも役立ちます。
4-3つなぎを使用
口の中に入れた食材がばらばらになってしまうと、飲み込みにくくなり誤嚥の可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐためには、つぶした食材同士をつなげるための卵や片栗粉、油などを活用します。
また、つなぎを使うと柔らかさを調整できるというメリットも。
歯の状態などにもよりますが、舌でつぶせる程度のほどよい硬さにするとよいでしょう。
05ソフト食の食材ごとの調理ポイント
ソフト食を作るためには、食材によって気を付けたい調理のポイントも異なります。
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
患者さんの状態に合わせてソフト食を作るには、まず嚥下機能の状態を確認することが重要です。
嚥下能力が低下していれば、極めてなめらかなペースト状の食事が適しています。
一方、咀嚼力がある程度残っている場合は、やわらかい食感の料理を提供するのがよいでしょう。
食材の選び方や調理方法を工夫することで、患者さんに合ったソフト食を提供できます。
食事形態は段階的に移行させ、患者の嚥下状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
ソフト食を通じて、患者さんの 生活の質の向上に寄与できるでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
3-1きざみ食:咀嚼機能の低い人
高齢者の介護食の中でももっとも最初に使われるのが「きざみ食」です。きざみ食は、普通食の食材を細かく刻んだ食事のことで、口がなかなか開きにくい人や、固いものを噛む力が弱くなっている人など、咀嚼機能が低下している場合に用いられます。
きざみ食は内容的には普通食とほぼ変わらないことや、何を食べているのかがはっきり分かることなどのメリットもありますが、口の中でばらばらになりやすく誤嚥を起こしやすいというメリットがあります。
最近、食べ物を食べると疲れてしまうという場合や、入れ歯に問題があるという場合に用いるのがよいでしょう。
3-2ミキサー食:嚥下機能の低い人
「ミキサー食」は、食材をミキサーにかけたもので、食べ物の形が残らないことが特徴です。
高齢者の場合、食べ物を噛む力だけでなく飲み込む力も衰えますが、ミキサー食は噛む力と飲み込む力が衰えた人向けの食事。単に食材をミキサーにかけるだけでなく、ゼラチンゼリーなどを使用することでより滑らかに喉を通る状態に仕上げられています。
ミキサー食は、咀嚼と嚥下の機能が低下している場合だけでなく、胃腸が衰えている場合でも消化と吸収が容易に行われるため、高齢者に向いた食事です。
また、ミキサー食で重要なのが水分。ミキサーを回すためにはある程度の水分が必要になるため、ミキサー食は通常よりも多くの水分を補給することができます。
しかし、多くの水分を使うとどうしても味が薄くなり、分量が増加。結果として、食事を残しがちになり、必要な栄養が補給できないということになってしまいます。
さらに、すべてをミキサーにかけてしまうことから、何を食べているのか分からないということになりがちです。
3-3ソフト食:咀嚼から嚥下までしやすい
ソフト食は一度食材をミキサーにかけているため、非常に柔らかい状態。そのため、咀嚼に問題がある人でもスムーズに食事を楽しむことができます。また、ミキサーにかけた食材を再び固めていることから、嚥下も簡単に行うことができます。
また、きざみ食のように誤嚥が起きる可能性も少なくなり、ミキサー食のように食欲が減退してしまうこともありません。
そのため、咀嚼と嚥下の双方または片方だけに問題がある場合にも用いることができます。
3-4導入ステップ
ソフト食は、身体の機能の衰えとともに導入するのが一般的。
ただし、いきなりすべての食事をソフト食にしてしまうよりも、普通食が難しくなったら、まずは食材の煮込み時間を長くしたり、圧力鍋を使用したりする軟菜食を用いましょう。
軟菜食は普通の食事と見た目は変わらないため、食事の楽しみが失われることもありません。また、あごやのどの筋肉を使うことから、衰えの速度を抑える効果も期待できます。
それでも軟菜食が難しい、食が進まないということになった場合、まずおかずのどれかをソフト食に置き換えて少しずつ慣れていくという方法がよいでしょう。
04ソフト食の作り方
高齢者にとってメリットの多いソフト食。では家庭でソフト食を作るときにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
4-1食材選び
ソフト食を作るときには、まず繊維の少ない食材を選ぶことが必要です。繊維質が多いものの場合、ミキサーにかけても繊維が残ってしまうことがあります。
もし肉や魚を使うときには、赤身の部分は避けて脂肪が多く含まれている部位などを選ぶとよいでしょう。
4-2調理の方法
調理を行うときには、片栗粉やゼラチンでとろみをつけることが必要です。もし汁物などがサラサラしていると誤嚥の危険性が高くなります。
また、飲み込みやすくするためにはオリーブオイル、ごま油やバターなどの脂質を使うという方法も。油の香りは食欲を刺激するので、食欲が減退しがちだという場合にも役立ちます。
4-3つなぎを使用
口の中に入れた食材がばらばらになってしまうと、飲み込みにくくなり誤嚥の可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐためには、つぶした食材同士をつなげるための卵や片栗粉、油などを活用します。
また、つなぎを使うと柔らかさを調整できるというメリットも。
歯の状態などにもよりますが、舌でつぶせる程度のほどよい硬さにするとよいでしょう。
05ソフト食の食材ごとの調理ポイント
ソフト食を作るためには、食材によって気を付けたい調理のポイントも異なります。
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
患者さんの状態に合わせてソフト食を作るには、まず嚥下機能の状態を確認することが重要です。
嚥下能力が低下していれば、極めてなめらかなペースト状の食事が適しています。
一方、咀嚼力がある程度残っている場合は、やわらかい食感の料理を提供するのがよいでしょう。
食材の選び方や調理方法を工夫することで、患者さんに合ったソフト食を提供できます。
食事形態は段階的に移行させ、患者の嚥下状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
ソフト食を通じて、患者さんの 生活の質の向上に寄与できるでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
4-1食材選び
ソフト食を作るときには、まず繊維の少ない食材を選ぶことが必要です。繊維質が多いものの場合、ミキサーにかけても繊維が残ってしまうことがあります。
もし肉や魚を使うときには、赤身の部分は避けて脂肪が多く含まれている部位などを選ぶとよいでしょう。
4-2調理の方法
調理を行うときには、片栗粉やゼラチンでとろみをつけることが必要です。もし汁物などがサラサラしていると誤嚥の危険性が高くなります。
また、飲み込みやすくするためにはオリーブオイル、ごま油やバターなどの脂質を使うという方法も。油の香りは食欲を刺激するので、食欲が減退しがちだという場合にも役立ちます。
4-3つなぎを使用
口の中に入れた食材がばらばらになってしまうと、飲み込みにくくなり誤嚥の可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐためには、つぶした食材同士をつなげるための卵や片栗粉、油などを活用します。
また、つなぎを使うと柔らかさを調整できるというメリットも。
歯の状態などにもよりますが、舌でつぶせる程度のほどよい硬さにするとよいでしょう。
05ソフト食の食材ごとの調理ポイント
ソフト食を作るためには、食材によって気を付けたい調理のポイントも異なります。
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
患者さんの状態に合わせてソフト食を作るには、まず嚥下機能の状態を確認することが重要です。
嚥下能力が低下していれば、極めてなめらかなペースト状の食事が適しています。
一方、咀嚼力がある程度残っている場合は、やわらかい食感の料理を提供するのがよいでしょう。
食材の選び方や調理方法を工夫することで、患者さんに合ったソフト食を提供できます。
食事形態は段階的に移行させ、患者の嚥下状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
ソフト食を通じて、患者さんの 生活の質の向上に寄与できるでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。

80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
5-1野菜
ソフト食の中心の食材となるのが野菜です。野菜はできるだけ繊維を少ないものを選ぶと食べやすくなりますが、繊維が少なすぎると便秘などが心配になるもの。
ある程度の繊維が含まれている食材を使用するときには、繊維を垂直に断ち切る方向でカットすると、繊維が短くなり、ミキサーに残ることがありません。
また、出来るだけ薄く食材をカットするように注意するとよいでしょう。
5-2魚
高齢者にとってうれしいのが魚を使ったメニューです。魚を選ぶときにはしっかり脂がのったものを選びましょう。脂質が含まれている油は加熱してもバラバラになりにくく、のど越しもよくなります。
また、魚の骨はあらかじめ取り除いておくこと。骨が残っていると、口腔内を傷付けてしまうことがあります。調理の際には、つなぎを利用してまとめていくと、バラバラにならず、まとまりやすく扱うことができます。
5-3肉
肉を選ぶときにも、脂肪が多い部分を選んだほうがよいでしょう。もし赤身などを選ぶ場合には、しっかり筋を切った上で、叩いてから調理すると繊維がほぐれて肉が柔らかくなります。また、食べやすいイメージのあるひき肉ですが、実際は加熱するとバラバラになりやすいもの。もしひき肉を使用する場合には、卵などをつなぎに加えて口の中でバラバラにならないようにしましょう。
01まとめ
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。


















